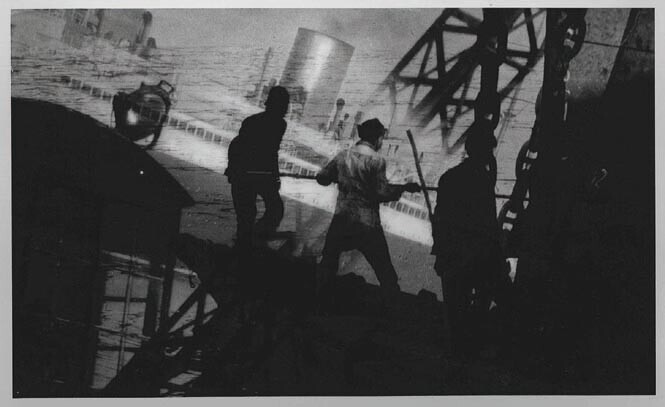(昨日の続き)
世界中の文学のルーツには悲劇がある。悲劇には、人間の心の深いところを揺さぶる力がある。だから後々まで伝承され、記憶が引き継がれる。
現代社会のように、人間の欲望を刺激するものが溢れ、悩みや不安を一時的に紛らわす娯楽に不自由しない状況でも、人のために尽くすことを願う人たちも多い。
欧米風に表現することが好まれる現代では、「コンパッション」という言葉が使われる。これは、相手を深く理解し、相手の役に立ちたいという純粋な思いを持ち、相手と共にある力のこと。
古代においても、この「コンパッション」の道を歩むものがいて、それが巫であった。
古事記において登場する女性の多くは、この巫であり、その多くは、悲劇的な存在として描かれている。
古事記の中では、とくに、「和邇氏」関係という設定の人物が、女性だけでなく男性でも多い。
その代表が、仁徳天皇に皇位を譲るために自殺した菟道稚郎子(うじのわきいらつこ)で、ヤマトタケルもまた、母親の播磨稲日大郎姫(はりまのいなびのおおいらつめ)が、和邇氏の娘である。
ヤマトタケルは、古代日本で最も有名な英雄ではあるが、父に恐れられ疎まれて、わずかな従者も与えらずに九州の討伐を命じられ、討伐から帰るとすぐに東方の蛮族の討伐を命じられた。そのためヤマトタケルは、父が自分に死ぬことを望んでいるのかと嘆く。そして、最期、望郷の歌を詠んで亡くなるわけで、明らかに、悲劇の主人公である。
和邇氏は、後に柿本氏や小野氏となるが、ともに歴史上に名を残す文学者を輩出している。
歴史探究の好きな人たちのあいだでは、和邇氏とか物部氏とかを古代の血族集団と捉え、その系図などを細かく辿る人たちも多いのだが、これは一種の職業集団であろう。
欧州では、ホメロスの時代から吟遊詩人と呼ばれる人たちがいた。彼らは定住者でなく、各地を旅しながら、歌や音楽とともに、物語を伝承していったが、日本でも同じだろう。
日本のような島国おいて、各地を自在に移動できるのは、縄文時代から自由に海を行き交っていた人たちで、それが後に海人族として束ねられていったのだが、彼らにも職能の違いがあり、安曇氏のように日本海側を主たる活動範囲として食膳と深い関わりを持つ勢力もあれば、紀氏のように、太平洋側で活動し、木材の調達に深く関わる勢力もあった。
日本列島は、黒潮にそった南側が森林資源が豊かであり、九州南部、四国、紀伊半島、伊豆にかけて木材を調達し船舶を製造する海人勢力は、森林資源を求めて海から河川深くに分け入っていく。河川沿いは、川が削り取った地質が剥き出してあり、鉱脈が見える。とくに船の防水と防腐に効果のあった辰砂=丹(硫化水銀)を欲していた彼らは、鉱山開発の人々でもあった。
辰砂がとくに豊富なところは、近畿の吉野から伊勢にいたるルートで、大和水銀鉱山(奈良県宇陀郡)は、明治時代まで採鉱が続いた日本最大の水銀鉱脈であり、伊勢国飯高郡丹生は、中世まで代表的な水銀鉱床だった。

現在でも、各地に丹生という地名が残るが、それらは、辰砂の採鉱現場である所か、辰砂と関わりの深い人々が拠点としていた所だった。
辰砂というのは、船の防水や防腐だけでなく、様々な用途がある。金の精錬も、水銀アマルガム法で行われるし、大仏などのメッキも水銀と金を化合させたものを全身に塗って、沸点の低い水銀だけ蒸発させる方法をとる。
そうした実用性だけでなく、古代から辰砂は、たとえば古墳の石室に敷き詰められてたり、刺青に使われていたことが魏志倭人伝に記録されたり、祭祀的にも用いられていたことがわかっている。神社の鳥居もそうだ。
辰砂の朱色は、血のように深い色で、古代人にとって、生命を象徴する色でもあったのだろう。
万葉の時代、辰砂の朱と白が特別な色として歌が詠まれた。
白は、「きよし」、「さやけし」。 朱の色を、「にほふ」、「てる」、「ひかる」、「はなやか」と詠まれた。
この朱と白が、日本の国旗であるが、神道の巫女が着用する衣装も、上半身の白い小袖と、下半身の赤い袴の組み合わせである。
「きよし」は、穢れがないことで、「にほふ」は、現在では嗅覚を意味するが、もともとは染色で花草木の色によく染まるという意味で用いられるなど、生命の力が照り映えるような状況である。
日本の国旗である日の丸のことについて議論される時、赤を「太陽」とだけ結びつけて、皇祖神に位置付けられるアマテラス大神の重ね、天皇を中心とする国家神道の象徴として捉えられ、そのことを支持するか、それとも反発するかという構図になってしまう。
しかし、赤と白は、巫の衣装でもあり、巫とは何なのかという視点から、このことを深く考えることも大切だ。
古来より巫女は神楽を舞ったり、神託を得て他の者に伝えるものと考えられていたので、神話において、天岩戸の前で舞いを行った天鈿女命(あまのうずめのみこと)が、巫女の原型とされている。
しかし、天岩戸に籠もったアマテラス大神も、別名が「オホヒルメノムチ(大日孁貴)」で、「ヒルメ(日孁)」の孁は、「巫」と同義であり、古来は太陽神に仕える巫女であったとも考えられている。
また、アマテラス大神の天岩戸籠りの原因となったスサノオの狼藉も、アマテラス大神が機屋で神に奉げる衣を織っていたとき、スサノオが機屋の屋根に穴を開けて、皮を剥いだ血まみれの馬を落とし入れたことであるが、織物をする女性は、古代の巫女を象徴する姿である。
古代、織物は、神や先祖霊に捧げる最高の供えものであった。布を織る者は、禊をして身を清め、布を織る場所も水辺であった。水は、穢れ祓いに通じている。
ニニギの天孫降臨の時、最初に出会ったコノハナサクヤヒメやイワナガヒメも水辺で機織りをしていた。そもそも、ニニギの母親の栲幡千千姫(たくはたちぢひめ)も機織りの神である。
身にまとう衣服は、依代であり、神や王のために織物を織る巫女には、それだけ神聖な力が求められたということになる。
全国的に存在する鶴の恩返しの伝承は、人間界の存在ではない鶴が、織物を通して、人間の老夫婦を豊かにする物語なので、巫女の物語の様相を帯びている。
この物語のなかで重要なポイントは、恩返しのために機織りを行う鶴が、自分の羽毛で機を織っているので、日に日に痩せ細っていくことだ。
巫の霊力が発揮されるのは、自己犠牲も厭わない「コンパッション=相手とともにあること」ゆえのことである。まさに、石牟礼道子さんの「悶えて加勢する」という言葉が、これに該当する。
巫は、自分の存在を打ち捨てる覚悟で神に仕えることで、その身に神を憑依し、神そのものになって、人々に豊穣をもたらし、人々を災難から守護する存在だった。
琉球王国では、17世紀まで、ノロによる神女体制が続いていたが、琉球神道における「ノロ」が、そうした古代の巫女の姿を今に伝えている。
そして、上に述べたように、辰砂(丹生)の朱色は、血のように深い色で、古代人にとって、生命を象徴する色でもあったゆえに、丹生と、巫女の結びつきは、いくつも見られる。
たとえば聖徳太子は、太子町の叡福寺に、なぜか二人の女性とともに埋葬されている。
一人は、母親の穴穂部間人。そして、もう一人が、最愛の妻の膳部菩岐々美郎女(かしわで の ほききみのいらつめ)である。
膳部菩岐々美郎女の実家、膳氏は、主に食膳を司り、軍や外交などでも活躍した海人系。
この膳氏の古墳が集中しているところが若狭の膳部山の麓で、上ノ塚古墳などがある。ここは、古代から遠敷(おにゅう)郡だが、7世紀後半の藤原宮の木簡では「小丹生評」と表記されており、ここもまた「丹生」であり、聖徳太子の妻、膳部菩岐々美郎女もまた、丹生の巫だった。

古代、丹生の巫は、その呪力によって王を支え、実家の海軍力でもまた王を支えていたが、政治の表舞台には立つことなく、陰で支えていた。
例外的に表舞台に立って活躍した神話上の人物が、新羅討伐を行った神功皇后(応神天皇の母)であるが、彼女に神が憑依して神託を告げるという内容が示されていることから、巫女であることがわかる。
神功皇后の本名は、息長足姫尊(おきながたらしひめのみこと)であるが、息長氏の聖域は、滋賀県の丹生(米原市)である。
丹生の巫と関わりが深い息長と、悲劇的な巫の伝承の多い和邇の結びつきを示しているのが、近江富士の三上山に降臨した天御影命の娘の息長水依姫と、彦坐王という和邇氏の血を引く皇子が結ばれたという神話伝承だ。
二人の子の丹波道主命の娘の日葉酢媛命(ひばすひめのみこと)が、第12代垂仁天皇に嫁いで景行天皇を生み、この流れが後の天皇の血統になると示されている。
さらに和邇氏は、全国にある浅間神社の総本社の富士山本宮浅間大社の神官として、皇祖神のニニギと結ばれたコノハナサクヤヒメを祀ってきた。コノハナサクヤヒメは、別名が神吾田津姫で、これは、南九州を拠点とする海人族の女神だが、和邇氏の祖も、吾田片隅命(あたかたすみのみこと)で、同じ吾田である。
これが史実かどうかわからないが、こうした伝承が残されていることじたいが、これら伝承の背後に、丹生と和邇の勢力が存在していたことを暗示している。
ここに書いたことを、3月31日と31日に京都で行うワークショップで、掘り下げます。
ーーーーーーー
3月30日(土)、31日(日)に、京都で開催するワークショップセミナーの詳細と、お申し込みは、ホームページにてご案内しております。
また新刊の「始原のコスモロジー」は、ホームページで、お申し込みを受け付けています。