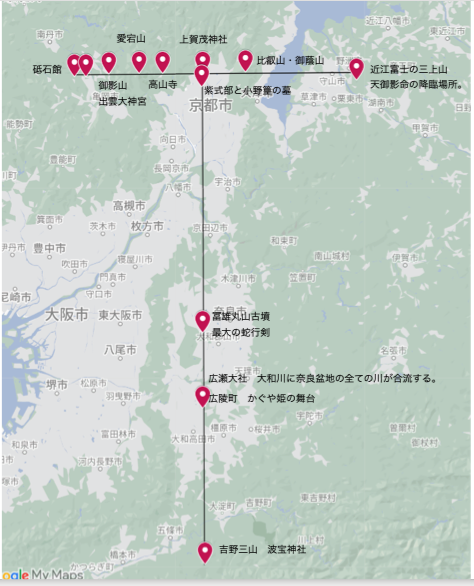古代に対する関心の持ち方は人それぞれだが、私は、卑弥呼のクニがどこにあったかということよりも、日本人の潜在的な心の在り方に関心がある。
日本の縄文時代は10000年も続いており、明らかに大陸の影響を受けたと思われる弥生時代以降の歴史は、その4分の1でしかない。だから、縄文時代の日本人の心が完全に消え去ってしまったとは思えず、それが、どのような形で今日まで引き継がれてきたのかを辿りたいという思いがあって、私は古代世界のフィールドワークに没頭している。
そして、その鍵を握るのは、海人だと思っている。海人というのは、海や川で漁を営むだけでなく、船を使って遠方と交流していた。
20世紀の人類学を切り拓いたとされるマリノフスキが、南太平洋のニューギニアでフィールドワークを行い、近代世界からは未開人とされた人々の洗練された思考を明らかにした。
彼らの文化は、近代西欧に比べて劣っているわけではなく、異なるだけで、非常に研ぎ澄まされ、豊かで、繊細な秩序を持っていた。
マリノフスキや、彼に続いたレヴィ=ストロースは、対象を外から眺めて上から目線で相手のことを結論づけるのではなく、対象の懐の中に入っていって、内側からその全体像を感じ取るというフィールドワークを対象を理解するための方法としたのだが、これは、人類学に限らず、どの分野においても重要な姿勢だと思う。
物事を頭の中だけで理解しようとすると、自分の常識や経験の範疇に当てはめて整理しがちになる。そうした理解は、自分の世界を広げることにつながらない。
これは、歴史を対象とする場合も同じ。過去の営みを、現代に比べて劣っていると現代人は考えがちだが、歴史のどの段階においても、それぞれの時代ならではの、非常に精密で豊かな秩序世界が築かれている。
マリノフスキの調査で興味深いのが、トロブリアンド諸島における「クラ交易」と呼ばれるもので、これは、ニューギニア島の東に広がる500kmほどの海域の島々を結ぶ交換の制度だ。
500kmというのは、日本では鹿児島から紀伊半島、そして紀伊半島から房総半島くらいの距離にあたる。
トロブリアン諸島の住民は、カヌーの船団を編成して、海域を時計回りと、反時計回りに移動しながら交流を行うのだが、このクラ交易の中心になるのが、時計回りの方は赤い貝の首飾りで、反時計回りの方では、白い貝の腕輪。これを欲する側は、これを手にいれるために出かけていく。しかし、どれだけ大変な思いをして手に入れても、自分の物として所有できず、しばらく保持した後、これを取りに来た別の島の人に渡さなければならない。そのようにして、この腕輪や首飾りは、島々のなかをゆっくりと移動していく。
現代的な「交易」は、何かを所有したい場合は、その見返りを差し出して自分の物にする。しかし、クラ交易で受け取ったり手渡したりする腕輪や首飾りは、お互いが行き交うためのモチベーション装置にすぎず、クラ交易は、別の島々の共同体を結び付けて、衝突を避けるための仕組みになっているのだ。
この交流のために、彼らは危険な航海に出るわけだが、出発の際には安全祈願の呪文を唱え、航海の途中も祈りを続ける。
20世紀になっても、この地球上には、こうした西欧近代とはまったく異なる文化の仕組みを維持していた人々がいたわけで、古代日本の海人も、もしかしたら、このトロブリアンド諸島の人々のような価値観で交流を行っていたかもしれない。
縄文時代の装身具で有名なのが糸魚川のヒスイだが、これは北海道から沖縄まで流通しているし、伊豆諸島南部の三宅島、御蔵島、八丈島に生息するオオツタノハノの貝を貝輪に仕上げたものが、北海道まで広域に分布していた。
海を行き交う人々の力なくして、こういうことはできなかっただろう。
そして、物の交換という形で各地と交流していた人々は、情報交換をも行っていたわけだから、後に、物語の伝承の担い手になっていっただろう。
日本の古代において、物語伝承に大きく関わっていただろうと思われる人々がいる。
それは、和邇氏と呼ばれる人たちで、この後裔が柿本氏や小野氏であり、多くの古代文学者を生み出している。
和邇氏は、祖を吾田片隅とし、吾田というのは、南九州に拠点を置いていた海人勢力とされている。
なぜ和邇氏が、物語伝承と深く関わっていたと考えられるのか?
それは、古事記などにおいて、もっとも多く登場するのが和邇氏関係であることや、歴史の節目となる重要な出来事に、和邇氏の陰が見え隠れしている(その多くが悲劇的主人公だが)からだ。
史実かどうかはともかく、古代の物語として特に重要な天孫降臨において、ニニギと結ばれたコノハナサクヤヒメは、別名が、神吾田津姫であり、これは、南九州の海人勢力である吾田の女神とされる。そして、このコノハナサクヤヒメを祀る代表的な聖域が、日本全国の浅間神社の総本社である富士山本宮浅間大社だが、この神職は、和邇氏の後裔である富士氏がつとめてきた。
また、これも史実かどうかはともかく、古代日本の英雄ヤマトタケルは、母親の播磨稲日大郎姫が、播磨風土記において、和邇氏の娘とされている。
そしてヤマトタケルの父、景行天皇は、丹波道主命の娘の日葉酢媛命(ひばすひめのみこと)だが、丹波道主命の父、日子坐王の母は、和邇氏の娘、意祁都比売命(おけつひめのみこと)である。
つまり、ヤマトタケルには、父母を通じて、和邇氏の血が流れていることになる。
仁徳天皇に皇位を譲るために自殺をした菟道稚郎子(うじのわきいらつこ)=宇治が聖域の母親も、和邇氏だ。
コノハナサクヤヒメに象徴されるように、女性を通じて、和邇氏の影響力が潜んでいる。
そして、神話のなかでコノハナサクヤヒメの父とされるのが大山祇神で、この神は、名前に山を含みながら、渡しの神ともされ、瀬戸内海の大三島が重要な聖域であるように、海上交通と大きく関与していた。山の神でもあるのは、船を造るためには山の樹木は欠かせないからだろう。
大山祇神は、伊豆周辺では三島明神とされ、その后神として、大島の波布比売、伊豆半島の伊古奈比咩命、神津島の阿波比売などがおり、阿波比売は、近畿や四国では天津羽羽神で、”はは”というのは蛇のことである。波布もまた、同名の蛇が南西諸島にいる。
古事記における大山祇神と結ばれ子を産んだとされるのは、野椎神(のづちのかみ)であり、これも蛇である。
縄文土器には蛇のモチーフが多く見られるが、縄文時代、蛇は聖なる生物であった。
大山祇神の后たちが蛇を象徴しているのは、大山祇神が、縄文時代からの海上交流に関係する渡しの神であるからだと思われる。
この大山祇神の娘のコノハナサクヤヒメと、他の文化圏からやってきた者の象徴であるニニギが結ばれた。神話は、日本の古代を、そのように伝えている。
そして、和邇氏(後の小野氏)の痕跡は、古代のまつりごとの中心であった畿内だけでなく、関東においても残されている。
武蔵国一宮は、聖蹟桜ヶ丘に鎮座する小野神社である。
小野神社から多摩川をはさんで対岸が、武蔵国の国府が置かれた府中だ。
そして、古事記において、ヤマトタケルが野火に囲まれた時、草彅の剣によって難を逃れた場所は相模国となっており、その候補地が、厚木市小野で、ここにも小野神社が鎮座している。
ヤマトタケルが船で房総半島に渡ろうとした時に嵐が起こり、それを鎮めるために妻の弟橘媛が犠牲となって入水するが、その前に詠んだ歌、「さぬさし 相武の小野に 燃ゆる火の 火中に立ちて 問ひし君はも」のなかに、「小野」の地名が記されている。
そして興味深いことに、聖蹟桜ヶ丘の小野神社と、厚木の小野神社を結ぶラインの延長上が神奈川県二宮町の吾妻山で、ここにコノハナサクヤヒメを祀る浅間神社があるが、この吾妻山には、入水した弟橘媛の櫛が海辺に流れ着いて、それを埋めて故人を偲んだという伝承もある。
この二宮町は、縄文時代の痕跡が多く残っているが、古墳も多く、全体では200近くが確認されている。しかし、他の地域のような土を盛り上げてつくる古墳は存在せず、丘陵の斜面に横穴を削って埋葬する横穴墓ばかりだ。
横穴墳は、全国的に見ると、内陸部には少なく沿岸部や重要河川沿いに多く作られている。
地域的には、大分、熊本、福岡、島根、静岡、神奈川、千葉、茨城、福島、宮城に多く、東京、埼玉、宮崎、石川、奈良が、これに続いている。
そして、横穴墓として全国的に有名なのが、埼玉県比企郡の吉見百穴で、200基を超える墓穴を見ることができる。

この場所は、聖蹟桜ヶ丘にある武蔵国一宮の小野神社の真北42kmである。そして不思議なことに、武蔵国の小野神社から、ヤマトタケルの野火の伝承がある相模国に小野神社を通って、弟橘媛の櫛が埋められたという伝承地で横穴墓が集中する二宮町までも42kmなのだ。

吉見百穴の場所は、内陸部であるが、荒川の水上交通路を使って東京湾まで出ることができる。そして、この群集墓がある小山からの見晴らしはよく、秩父の山々から富士山まで一列に望むことができる。古代の関東もまた、河川交通と海上交通によって、各地が結ばれていた。
(続く)
ーーーーー
日本文化と日本の祈りの本質を掘り下げる。
4月27日(土)、28日(日)、東京で、ワークショップセミナーを開催します。
詳細と、お申し込みは、ホームページにてご案内しております。
また新刊の「始原のコスモロジー」は、ホームページで、お申し込みを受け付けています。